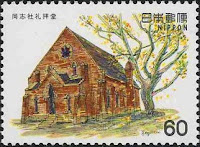教え子のK大のO君から、メールがあった。秋にアフリカか南米に行くつもりだという。バックパッカーではなく、友人(彼女も私の教え子でブラジルに行っている。)から教えてもらったボランティアツアーに参加するつもりらしい。で、その行き先について意見を求めてきたのだった。まことに嬉しいではないか。
その候補がまた面白かった。タンザニアのアルーシャ。ガーナのアクラ。エチオピアのアディスアベバ。ボリビアのコチャンバンバ。これまで文献で読んできたコトと、現状を肌で感じてくることを目標にしているとのこと。ますます面白いではないか。
で、私はニコニコしながら返信した。私が勧めたのは、タンザニアのアルーシャである。アフリカに行くとすれば、まず東アフリカから攻めるのがいいと私は思っている。まず、英語圏であるということ。一般の人々も、ブロークンでも英語を解するので、多少なりとも語り合うことが可能だ。気候も高原なら過ごしやすい。エチオピアは、その点できびしい。アムハラ語は難しい。しかも、古い単性論のエチオピア正教会の世界なので、少しばかりアフリカに行ったという時、少々特殊な趣があるのである。ガーナもいい。英語圏だし。しかし、気候がかなり厳しい。暑い分、風土病も多い。ボリビアは、南米の中でも息子のあこがれの地であるが、思い切り治安が悪い。あの息子がビビッているくらいだから、ちょっと勧められない。O君はスペイン語ができるので、いいかもしれないが、私としては勧められない。
タンザニアはいい。なにより、アルーシャだというのが良い。アルーシャは、初代大統領ニエレレが、独立宣言(タンガニーカ時代)や、サンジバルとの合併(現在のタンザニア)した歴史的都市でもあり、なによりウジャマー社会主義を宣言(アルーシャ宣言)した地である。結局、ウジャマー社会主義は失敗するのだが、その理想に燃える姿勢は、タンザニアを国民国家とすることに成功した。タンザニア人は、ケニアやウガンダみたいにエスニックグループが大きく幅をきかさない。我々は、タンザニア人だと称する。もちろん出自のエスニックグループも民族語も存在しているが、スワヒリ語と英語を主に話し、多民族ながら国民国家となったアフリカでは稀な社会である。しかも、キリマンジャロの近くにある。登るのは大変だが、その雄姿を見ることは十分可能だし、コーヒーのプランテーションもある。(但しキリマンジャロ・コーヒーの産地だが、現地で飲めるのは三級品らしい。)
というわけで、私は熱烈にアルーシャを推したのだった。どうやら、O君もその気になったらしい。イエローカードが、今は必要ないらしいが、打っておいた方がいいと思う。(10年有効やし。)マラリアの薬は現地で調達すべし、などと返信したのだった。タンザニアは面白い。資料もたくさんある。ウジャマー社会主義など行くまでに調べておくとかなり面白い。是非ともタンザニアを知るための60章を読んでみてほしい。フフフ。いいなあ。キリマンジャロの雪は、さらに少なくなっているのだろうか。
2011年7月4日月曜日
梅田のJ堂書店にて
 |
| J堂書店のあるビル |
と、いうわけで、昼から振り替え休日(国際理解教育学会の発表を日曜出勤扱いにしてもらえた故)を取ったのである。
こういう日は、必ず本屋に行く。放出駅で「さあ、京橋まで出てK書店に行こか」と、ふと料金表を見たら、『北新地』まで行くのと10円しか違わない。ならば、もっと大きいJ堂書店に行くことにした。通勤で読む文庫本を探すだけでなく、せっかくJ堂に行くのなら、アフリカや開発経済学関係の新刊が出てないかを確認することにした。
梅田のJ堂書店には莫大な文庫本があるので、かなり目移りする。金さえあれば大いに散財したいところだが、そうもいかない。結局太めの2冊を購入した。1冊は、かなり以前(2003年初版)の本で『刑務所の王』(井口俊英/文春文庫)、もう一冊は本年6月10日初版の佐藤優の『交渉術』(文春文庫)である。できればゆっくりと読んでから書評をまた書きたいところである。
その後、アフリカ関係と、開発経済学関係の書棚を覗いてみた。だいたいここの書棚は値段が高いので、手帳にメモするだけのことが多いのだが、今日は思わず買ってしまった。『世界一大きな問題のシンプルな解き方-私が貧困解決の現場で学んだこと』(ポール・ポラック/英治出版)である。この本は開発経済学の学術書ではない。『従来から行われてきた政府や国際機関主導のトップダウン型の大規模な国際開発とは異なり、現地の人々の目線に立ったボトムアップ型のアプローチである。現地の人たちが何を必要としているかを見極め、それを持続可能な形で提供し、貧困から脱却する手助けをすることだ。』(日本語版への序文より)
以前5月21日付ブログで書いた室井先生の視点や、6月18日付ブログで書いた大山先生の視点と共通するものがある。私の開発経済学の興味が、脱政府支援の方向に向いてきているのは確実である。うーん、読んで見たい、という気持ちが抑えられなかったのである。あちゃー。また妻に…。
2011年7月3日日曜日
秒読 文庫本 「動物の値段」
先週の金曜日、奈良まで所用があって行ってきた。ちょうど『都市を生き抜くための狡知ータンザニアの零細商人マチンガの民族誌』を読みえた直後で、帰りの電車で読む本がなくなった。困って本屋に駆け込んで文庫本を買い求めた。『動物の値段』白輪剛史/角川文庫)という本である。
著者は、動物商で、動物園や水族館、ペットショップなどに世界各国の野生動物などを卸している人である。なかなか面白い商売である。いわゆるワシントン条約や、検疫の話など普段では知り得ない話が書かれている。輸送方法やその費用などが莫大にかかる動物は、その費用も価格に反映されるわけだ。なるほど…である。
私は、子供のころ、イヌやカメや文鳥などを人並みに飼っていたことがある。ただし、飽きっぽいのか、世話をしくなるので、今は亡き母親によく怒られた。以来、ペットとは無縁の生活を送っている。
一番印象に残ったのは、ピグミージェルボアの話である。パキスタンから著者が初めて輸入して大当たりした、500円玉くらいの小さなトビネズミである。小さい、かわいい、臭わない、おとなしいというパーフェクトなペットである。卸値29800円。小売り価格6万円ほど。しかしアフガンのカンダハル近くに生息するわりに弱い動物で、大ヒットしたものの、数年後には暴落(2000円くらい)、さらにネズミ類の全面輸入禁止という憂き目にあった動物らしい。
ところで、イグアナ。私は飼いたいとは思わないが、意外に安く2980円だとか。雑草や果物も食べるし、ペットショップにはイグアナフードも売っているらしい。ただ、3年で大人になり、最終的には2mくらいになるらしい。でもほとんどそれまでに死んでしまうのだとか。
そんな私でも、『ナマケモノ』は飼えそうだと思った。キュウリが好きだそうだ。問題はカビ臭いことと、25℃くらいの温度にしておくこと。また、なめてかかると噛みついたりすることがあるらしい。ただし価格は65万円。
…もし、65万円もオカネに余裕があるなら、私はアフリカに人間を見に行く。(笑)
著者は、動物商で、動物園や水族館、ペットショップなどに世界各国の野生動物などを卸している人である。なかなか面白い商売である。いわゆるワシントン条約や、検疫の話など普段では知り得ない話が書かれている。輸送方法やその費用などが莫大にかかる動物は、その費用も価格に反映されるわけだ。なるほど…である。
私は、子供のころ、イヌやカメや文鳥などを人並みに飼っていたことがある。ただし、飽きっぽいのか、世話をしくなるので、今は亡き母親によく怒られた。以来、ペットとは無縁の生活を送っている。
一番印象に残ったのは、ピグミージェルボアの話である。パキスタンから著者が初めて輸入して大当たりした、500円玉くらいの小さなトビネズミである。小さい、かわいい、臭わない、おとなしいというパーフェクトなペットである。卸値29800円。小売り価格6万円ほど。しかしアフガンのカンダハル近くに生息するわりに弱い動物で、大ヒットしたものの、数年後には暴落(2000円くらい)、さらにネズミ類の全面輸入禁止という憂き目にあった動物らしい。
ところで、イグアナ。私は飼いたいとは思わないが、意外に安く2980円だとか。雑草や果物も食べるし、ペットショップにはイグアナフードも売っているらしい。ただ、3年で大人になり、最終的には2mくらいになるらしい。でもほとんどそれまでに死んでしまうのだとか。
そんな私でも、『ナマケモノ』は飼えそうだと思った。キュウリが好きだそうだ。問題はカビ臭いことと、25℃くらいの温度にしておくこと。また、なめてかかると噛みついたりすることがあるらしい。ただし価格は65万円。
…もし、65万円もオカネに余裕があるなら、私はアフリカに人間を見に行く。(笑)
タンザニアのマチンガの話 3
 |
| ブルキナのワガの「マチンガ」たち スコールがあがった後動き出す |
卸売商「(販売枚数)は5枚か…。」(支払い金額が300シリング足りない)小売り人「それは今日のウガリ(昼食代)に消えた。そしてオレは、今日の夜は空気を食べるんだ。」卸売商「エマは7枚、ドゥーラは帰ってこない。ここのところ、いったいどうなっているんだ。」(卸売商はポケットに支払い代金をしまう)小売り人「おい、(仕入れ代金を)全部持っていくのか?友だち(自分のこと)は(夕飯に)空気を食べるのにお前はビールで乾杯かよ。」卸売商「文句ばかり言うなよ。俺だってたいへんなんだ。今週は全然売れてないんだ。」小売り人「へこむなよ。ここ最近、客のみんなが、カネがないって嘆いているんだよ。1枚1250シリングでは売れないことを理解しろよ。」卸売商「じゃあ、1200シリングずつにすれば満足なのか?」小売商「1000、1000にしてくれれば、明日もこれ(今日の売れ残り)を売ってやるよ。」卸売商「なら、今日は1200ずつ返してくれればいいさ。でも明日もとりあえず1200シリングずつで粘ってみろよ。」小売り人「じゃあ、オレのカネくれよ。」卸売商「わかった。(卸売商は、5枚×50シリング=250シリングではなく、生活補助として2000シリングを渡した)明日は早く帰ってこいよな。」
小売商にとって、ウジャンジャ(狡知)な交渉とは長々と言い訳を並べることではない。「友だちは空気を食べるのにお前はビールで乾杯かよ。」などのコトバは、互いの境遇の不平等や自らの置かれた状況を端的に表している。ウィットのきいた文句やことわざ、格言を駆使して、個別の事情を普遍的な理に変換することも、よく観察されるそうだ。
この信用取引(マリ・マウリ取引)は、資本ゼロで小売り人はスタートする。しかも売れなければ返品可能、生活援助も必要である。資本主義的な通常の発想では、中間卸売商は極めて不条理な立場におかれている。しかも、ひどい時は、小売り人はそのまま商品を持ち逃げすることもるのである。この中間卸売商と小売り人は、血縁や地縁でつながっていないことが常である。全く初めて会った人間とも取引が行われる場合もある。(小川さんの詳細なデータで証明されている。)なぜ、このような不確実な取引を行うのか?以下、小川さんの推察である。
中間卸売商は、「ビジネスはギャンブルだ」と確信していて、小売商に能力主義を採用しないのである。その理由は、①小売商の販売結果が思わしくないのは、必ずしも本人の販売努力や販売能力の問題ではなく、、ある程度は運の問題だと認識していること。②中間卸売商たちが不確実な都市社会を生きるマチンガとしての仲間意識のうえに小売商の事情と行為に共感していること。③中間卸売商自身がこのような方法でうまく稼ぐことに自信をもっていること。だから、このマリ・マウリ取引というゲームを動かすために、ウジャンジャな嘘や騙しを織り込みずみのものと考えているのだ。ただし、その嘘や騙しには、適切なタイミングがあり、適切なやり方があることを理解しているものがムジャンジャ(ウジャンジャを身に付けた者)なのである。
実際、小川さやかさんは、小売り商も、中間卸売商もやっておられる。後半に出てくるが、この取引、無茶苦茶難しいらしい。結局、何も考えず、その場になって初めて対応する方がいいそうだ。その場の空気を読んで、全精力であたると、ウジャンジャなやり取りが出てくるらしい。
最後の最後に、小川さんは、このウジャンジャ、日本にもあるよね~と書いておられる。窮鼠猫を噛む。追いつめられた生徒のウソを見抜きながら許すことも多かったなあ。30年も教師をやっていると…。騙されるのも教育のうちなんて、自分を正当化してきた。(笑)でもその余裕が、生徒との信頼関係を形成していくのである。これって、中間卸売商的ウジャンジャ?
2011年7月2日土曜日
同志社大学の英断
私は、いつも朝時間に余裕がないので夕方に朝刊を読むことが多い。今日は土曜日で休みだったのだが、日ごろの習慣で、またまたそうなった。相変わらず、政治面を読んで暗澹たる気持ちになるし、なでしこジャパン、凄いな、などどと思ってめくっていくと、最終面に、まことに個人的に大きな朗報が載っていた。
『博士課程無償化へ・同志社大学「すでに受給」でも奨学金支給』
来年度から、同志社大学の博士課程後期で、ほぼ全学生に学費などに相当する奨学金を支給し、実質無償化すると発表した。他の機関から奨学金を受けていても対象となる。全国初の制度という。後期博士課程入学時で34歳未満の学生が対象で、(中略)神学、文学、社会学などの文系は総額223万円、(中略)返済不要。対象は在学中の学生も含め約200人。(後略)
うひゃひゃひゃと私は笑った。この約200人の親の一人だからだ。息子は、某所から奨学金(研究費)も受けている。詳細は妻に任せてあるが、我が家の家計の負担が少なくなることは確からしい。
博士課程後期に進む学生が、不況のあおりを受けて、全国的に危機的に瀕しているらしい。たしかに、学問をするのには金がかかる。海外の大学では、生活費も含めて優秀な学生を集めるらしい。同志社の学生支援センターの英断に感謝したい。
これで、来年こそは、夫婦で、結婚31周年記念海外ツアー実施じゃあー。
『博士課程無償化へ・同志社大学「すでに受給」でも奨学金支給』
来年度から、同志社大学の博士課程後期で、ほぼ全学生に学費などに相当する奨学金を支給し、実質無償化すると発表した。他の機関から奨学金を受けていても対象となる。全国初の制度という。後期博士課程入学時で34歳未満の学生が対象で、(中略)神学、文学、社会学などの文系は総額223万円、(中略)返済不要。対象は在学中の学生も含め約200人。(後略)
うひゃひゃひゃと私は笑った。この約200人の親の一人だからだ。息子は、某所から奨学金(研究費)も受けている。詳細は妻に任せてあるが、我が家の家計の負担が少なくなることは確からしい。
博士課程後期に進む学生が、不況のあおりを受けて、全国的に危機的に瀕しているらしい。たしかに、学問をするのには金がかかる。海外の大学では、生活費も含めて優秀な学生を集めるらしい。同志社の学生支援センターの英断に感謝したい。
これで、来年こそは、夫婦で、結婚31周年記念海外ツアー実施じゃあー。
タンザニアのマチンガの話 2
 |
| ブルキナ・ワガの『マチンガ』 なぜが女性下着屋さん |
マチンガというのは、タンザニアの都市で、様々なもの(古着とか時計とかバッグとか)を小売りする商人のことである。こういう人々を、私はケニアやジンバブエやブルキナファソでたくさん見た。要するにインフォーマルセクターに従事する人々なわけだ。だいたい30歳台くらいまでの若者が多い。彼らは、卸売商から商品を受け取り、それを販売する。路上でシートを広げて販売したり、商品を持ち歩いて行商したりする。儲けは少なく、せいぜい日々の生活費を稼げる程度である。
彼らの商売は面白い。この本に書かれている古着販売では、卸売商は、マチンガと信用取引を行っている。つまり、古着の中からグレード(6月26日付ブログ参照)ごとに、いくらといった商品の値段の基準を決め、手渡す。その日のうちに売れた枚数分の金額をマチンガは卸売商に渡すわけだ。たとえば、その日のグレードAは1500シリング、Bは1000シリング、Cは500シリングだとする。マチンガは、Aを2000シリングで売ったとすると500シリングの儲け、Bを1200シリングで売ったとすると200シリングの儲けになる。だが、ここが面白い。金のありそうな客からは、うまく騙して(?)Aを3000シリングで売ることもある。反対に、貧乏な客からはCを卸値の500シリングで売ったりもする。その客によって価格を変えるのは当たり前である。もちろん売れ残ったり、ひどい時はまったく売れない時もある。こういう時、卸売商は、マチンガの返品を受け付けるし、生活費を援助したりすることもある。この信用取引をマリ・カウリ取引というらしい。
この辺の、客とのやりとり、さらに卸売商とのやりとりが、ウジャンジャと呼ばれる狡知である。これが面白い。口八丁手八丁、一瞬の機知。会話の裏の真意を見抜く知恵。
ちょっと、具体例をあげよう。顔見知りの日雇労働者とマチンガとのやりとり。
客「いくら?」小売商「1800シリング、おれのお客さん」客「ちっ、なんでそんなに高いんだよ。1000シリングでどうか。」小売商「1000シリングじゃ儲からない。オレの親友、あんただって、服の値段くらい知っているくせに。」客「頼む、1000シリングで同意してくれよ。俺たちディ・ワーカーだろう。最近、俺本当に運がないんだよ。」小売商「友達よ、死にそうなんだよ。あんたの値段じゃ、オレが死んじまう。1500シリングにしようぜ。」客「わかった。そんじゃまたな。」小売り商「おい、ちょっとだけ足してくれよ。」客「もういいよ。俺ほんとに金ねえもん。」小売商「わかったよ、出せよ、その金。」
結局、この顔見知りの客に1500シリングの値で卸売商から仕入れたAグレードの古着を1000シリングで売ったのである。この会話には、数々のスラングが使われているらしい。そのスラングからマチンガは、客が本当に金がない状況を瞬時につかみ取り、将来常連客となるとふんで、赤字をだしながら販売したのである。こういう客の判断を『リジキ』というらしい。
閉話休題。ブルキナのワガで、私は地図や教材のためのブルキナの英語のガイドブックを、ワガの「マチンガ」から買った。たしか地図が日本円になおすと1枚1000円、アトラスが2000円だった。Iさんの紹介なので無茶はしてないだろうが、きっと私の『リジキ』を彼らは、それくらいなら買うだろうと判断したのだと思う。どっちみち、ブルキナに金を落とせるだけ落とすつもりだったので文句はないが、きっとそうだ!と私はそんなことを考えて、読んできたのだった。
とてもとてもこんな短いブログでは語りつくせない。…つづく。
2011年7月1日金曜日
I want to ride my bicycle.
 |
| 放出駅/不動産屋さんのHPより拝借 |
昨日は、かなり晴天だった。ストロングな太陽が朝からガンガン照りつける。ところが、車輪の小さな私の自転車でも、一応風をきって走る。ちょっと運転するのには不安定だが、なかなか爽快であった。
今日は、放出駅を出るとポツポツと雨。傘をさすほどではない。そのまま駐輪場に行き、自転車の鍵を外し、モーニングへ。私の愛用のアフリカ・コレクションの鞄(4月3日付うログ参照)は、そこそこ大きい。前使っていたパソコンが入るほどの大きさである。カゴなどつけていないので、たすき掛けで自転車をこぐ。1分もしないうちに喫茶店についた。ところが、モーニングを終えて外へ出ると、かなり雨脚が強くなっているではないか。鞄にレインカバー(これも、ナショナルジオグラフィック・オリジナル)をつけ、傘をさして運転することになった。なかなか危ない。(笑)もともと不安定なのに、さらに不安定である。だが、3分ほどで学校に着いた。思ったより苦痛ではない。「どしゃぶりならともかく、少々の雨なら、自転車やな。」と、心の中でつぶやいた私であった。
登録:
投稿 (Atom)