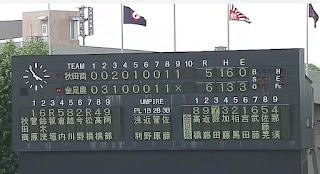|
| https://saintmarks.org/2023/12/a-forum-on-the-book-of-common-prayer/ |
「鳥瞰するキリスト教の歴史ー宗派・教派の違いがわかるー」(岩城聰/ペレ出版)による聖公会(=英国国教会・アングリカン)の考察の第4回目。著者は、聖公会の宗教改革の大きな特徴として、「提題」(ルターの95箇条の提題が有名。提題とは命題を提起すること/主張)や「信仰箇条」(1563年のエリザベス1世の信仰箇条が有名。教会が認める信仰、信仰告白、中心的教義を箇条書きにまとめたもの)同士のぶつけ合いや論争によってではなく、礼拝時に用いる「祈祷書」によって、神学者や聖職者だけでなく、一般信徒も巻き込んで改革が進められたことだとしている。
ちなみに、エリザベス1世の信仰箇条とは、カンタベリー大主教に任命したマシュー・パーカーが42箇条のラテン語版を主教会議に提出したが、議会(上院と下院)が39箇条に改正して承認された。英語版が出版されたのは、1571年。ルター派のアウグスブルグ信仰告白や、ツヴィングリ・ブリンガー・カルヴァンなどの影響を受けている。ただ祈祷書と職制に関しては、彼らとは解釈が異なる。つまり、聖公会の他のプロテスタントとの相違は、この”祈祷書と職制”であると見て取れる。
さて、その「祈祷書」は、前述のようにエドワード6世時代・シーモアの主導で、1549年の「礼拝統一法」が議会で可決され、当時のカンタベリー大主教・クランマーが編纂した祈祷書(第一祈祷書)が使用されることになった。クランマーは、序文の中で、祈祷書の原則について、①聖書に基づいていること。②原始教会の慣行に合致していること。③国内における礼拝の統一を目指すもの礼拝であること。④民衆の利益になるものであることを挙げている。
さらにシーモアを失脚させたダドリー主導で、1552年、議会は「第二礼拝統一法」・「第二祈祷書」を可決、さらにプロテスタント的な方向へ宗教改革を推し進める。カトリックの慣習、動作、服装、装飾は極力取り除かれ、礼拝の際に着用する祭服も簡素化された。この時は礼拝への参加の義務化、違反者には厳しい罰則が課された思想統制ともいえるデメリットもあったが、英語による礼拝と聖書に基づく信仰を広め、実質的な宗教改革を推し進めたというメリットもあった。さて、この第二祈祷書は、その後多少の改定があり、現在も使われている第五祈祷書(1662年)におよぶのだが、その土台となっている。
少し調べてみた。祈祷書とは、祈祷、礼拝、儀式における手順を示した規則書で、誕生・洗礼・婚姻・葬儀まで、また日々の起床から就寝までの公的・私的の信仰生活について書かれている。この1冊だけを用いるのが聖公会の大きな特徴である。ところで、第一祈祷書では、ラテン語によるミサに、英語によるこの祈祷書の内容がが追加されていたようだ。
エリザベス1世は、1559年に祈祷書を新しくしている。カトリックへの歩み寄りが見られる祈祷書で、①祝祭日を典礼暦に追加、②教皇のための祈りを削除、③聖職にたいして伝統的な式服を着用、などの変化があった。①の典礼歴というのは、キリスト教の暦のことで、カトリックではかなりの数の記念日がある。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E4%BC%9A%E6%9A%A6
先日、学院の宗教科の先生が、ルター派がカトリックに最も近いと言われていたことを記したが、ルター派は、カトリックの典礼暦をほぼ守っているようである。カルヴァン派にはこの典礼暦を否定する宗派も多いのだが、聖公会はルター派と同じくらいの記念日を設けている。
第五祈祷書(1662年)は、司祭12名が集まり見直しを討議したが結局まとまらず、議会にて、第一祈祷書から600点におよぶ改定が行われた。著者が、この祈祷書は、”一般信徒も巻き込んで改革が進められた”としているのは、この議会での討議を指すのであろうと私は思う。たしかに、興味深い特徴だ。
なお、聖公会のもうひとつのプロテスタントとの相違である”職制”は、主教(聖公会と正教会に存在する)、司祭(聖公会とカトリック、正教会に存在。聖公会でも神父と呼ぶ。)、執事(カトリックの助祭に近い)という三段階で、プロテスタントの”職制”とは大きな相違がある。